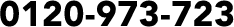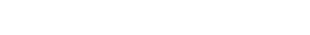医学部再受験と編入を比較!社会人や卒業見込みではどちら選ぶべきか

社会人として働いた後、あるいは他の大学を卒業した後に医学部を目指す場合、一般入試を受ける「再受験」と、大学卒業者を対象とした「学士編入」という2つの道があります。どちらを選ぶべきか悩む方は非常に多く、それぞれにメリットとデメリットが存在します。
再受験と学士編入は、入試科目や受験資格、入学後の年数など、様々な点で大きく異なります。自分の状況や学力、目標に合わせて最適な選択をすることが、医学部合格への近道となります。間違った選択をすると、貴重な時間を無駄にしてしまう可能性もあります。
本記事では、医学部再受験と学士編入の違いを詳しく解説し、それぞれの特徴やメリット・デメリット、そしてどのような人にどちらが向いているのかについて具体的に紹介します。これから医学部を目指す社会人や大学卒業者の方にとって、最良の選択をするための指針となる内容をお届けします。
医学部における再受験と編入の違い
医学部を目指す際の再受験と学士編入には、入試制度から入学後のカリキュラムまで、様々な違いがあります。まずは主要な違いを一覧表で確認してみましょう。
医学部再受験と学士編入の比較
| 項目 | 再受験(一般入試) | 学士編入 |
|---|---|---|
| 受験資格 | 高校卒業または同等の資格があれば誰でも可能 | 四年制大学卒業または卒業見込みの者 |
| 入学年次 | 1年次から | 2年次または3年次から |
| 卒業までの期間 | 6年間 | 4年から5年間 |
| 試験科目 | 英語、数学、理科2科目、国語(共通テスト)など | 主に英語、生命科学、面接、小論文 |
| 募集人数 | 一般入試の枠で数十名から百名以上 | 数名から十数名程度 |
| 実施大学数 | すべての医学部で実施 | 一部の大学のみ実施しつつも拡大傾向 |
| 競争率 | 大学により幅広い(2倍から20倍以上) | 非常に高い(10倍から40倍以上) |
| 年齢への寛容度 | 大学により異なるが、再受験制限を設ける大学も一部ある | 比較的寛容で、年齢制限も緩い傾向 |
| 数学の必要性 | 必須(共通テストと二次試験) | 英語・生命科学中心だが、数学や物理・化学を課す大学もある |
| 学習範囲 | 高校全範囲 | 生命科学系が中心 |
この表からわかるように、再受験は高校レベルの幅広い学習が必要な一方、卒業まで6年かかります。学士編入は試験科目が絞られていますが募集人数が少なく競争率が高いという特徴があります。
再受験の場合、共通テストでは国語や社会も必要になるため、理系科目だけでなく文系科目の対策も必要です。一方、学士編入では数学が不要な大学が多く、生命科学と英語に集中して学習できます。ただし、学士編入は実施している大学が限られており、選択肢が狭まるというデメリットもあります。
入学後のカリキュラムにも違いがあります。再受験で1年次から入学すると、若い学生と一緒に基礎医学から学び始めます。学士編入で2年次や3年次から入学すると、すでに進んでいるカリキュラムに途中から参加することになるため、独学で追いつく努力が必要になる場合もあります。
経済面では、学士編入の方が在学期間が短い分、学費や生活費の総額は少なくなります。ただし、学士編入の準備にも時間がかかるため、トータルで考えると必ずしも学士編入の方が早く医師になれるとは限りません。
医学部再受験の特徴
医学部再受験とは、一般入試を通じて医学部を目指す方法です。高校を卒業してから時間が経った社会人や、他の大学を卒業した方が改めて医学部一般入試に挑戦するケースを指します。
再受験の特徴を理解することで、自分にとって適切な選択かどうかを判断できます。ここでは、医学部再受験の主要な特徴を5つ解説します。
- すべての医学部が受験可能で選択肢が広い
- 高校範囲全体の学習が必要となる
- 共通テストと二次試験の両方を突破する必要がある
- 大学によって再受験生への寛容度が異なる
- 6年間の学生生活を送ることになる
すべての医学部が受験可能で選択肢が広い
医学部再受験の大きなメリットは、すべての医学部が受験対象となり、選択肢が非常に広いことです。国公立大学は約50校、私立大学は約30校の医学部があり、そのすべてに挑戦できます。
学士編入は実施している大学が限られているため、地理的な制約や大学の特徴による選択肢の狭さに悩むことがあります。しかし再受験なら、自宅から通える大学、地域医療に力を入れている大学、研究環境が充実している大学など、自分の希望に合った大学を幅広く選べます。
また、複数の大学を併願できることも大きな利点です。国公立の前期日程と後期日程、さらに私立大学を複数受験することで、合格のチャンスを増やせます。特に私立大学は日程が重ならなければ何校でも受験できるため、実力に応じて挑戦校から安全校まで戦略的に受験校を組み立てられます。
さらに、各大学の入試傾向を研究して、自分の得意分野が活きる大学を選ぶことも可能です。数学が得意なら数学の配点が高い大学、英語が得意なら英語重視の大学を選ぶといった戦略が取れます。このように、多様な選択肢の中から最適な大学を選べることが、再受験の大きな強みといえます。
高校範囲全体の学習が必要となる
再受験の大きな特徴であり、同時に大変な点は、高校で学ぶすべての範囲を学習しなければならないことです。共通テストでは、英語、数学、国語、理科、社会の5教科7科目が必要となります。
特に社会人として長く働いていた方にとって、高校時代に学んだ内容は大部分を忘れているでしょう。数学の公式、古文や漢文の文法、理科の法則など、一から学び直す必要があります。さらに、二次試験では記述式の問題が出題されることが多く、ただ暗記するだけでなく深い理解が求められます。
文系出身者にとっては、理系科目の学習が特に高いハードルとなります。数学三まで必要な大学が多く、物理や化学といった理系科目も一から学ばなければなりません。逆に理系出身者でも、国語の現代文、古文、漢文や、社会科目の学習に苦労することがあります。
学習範囲が広いということは、それだけ準備期間も長くなるということです。最低でも一年から二年、場合によっては三年以上の準備期間が必要になることもあります。働きながら勉強する場合は、さらに時間がかかるでしょう。広範囲の学習を計画的に進める忍耐力と時間が、再受験には不可欠です。
共通テストと二次試験の両方を突破する必要がある
国公立大学の医学部を目指す場合、共通テストと二次試験という二段階の試験を両方とも高得点でクリアする必要があります。どちらか一方だけ良い点数を取っても合格できません。
共通テストは毎年1月中旬に実施され、五教科七科目の試験を二日間で受験します。医学部では共通テストで約85パーセントから90パーセントの得点率が必要とされることが多く、非常に高い水準が求められます。一科目でも大きく失敗すると、その時点で合格が難しくなります。
共通テストをクリアした後、二月下旬から三月上旬にかけて各大学の二次試験があります。二次試験は記述式が中心で、数学の証明問題や、理科の論述問題など、深い思考力を問う問題が出題されます。共通テストとは異なる対策が必要であり、両方に対応できる実力を養わなければなりません。
私立大学の場合は共通テストを利用しない独自試験もありますが、その場合も各大学の出題傾向に合わせた対策が必要です。大学によって問題の難易度や形式が大きく異なるため、志望校の過去問を徹底的に研究することが重要です。
このように、再受験では複数の試験形式に対応できる総合的な学力が求められます。一発勝負の試験で実力を発揮するプレッシャーに打ち勝つメンタルの強さも必要となります。
大学によって再受験生への寛容度が異なる
医学部再受験において注意すべき点は、大学によって再受験生や高年齢受験生に対する姿勢が異なることです。公式には年齢差別をしないと表明していても、実際の合格者データを見ると傾向が見えることがあります。
一部の大学では、合格者のほとんどが現役生や一浪生で占められており、再受験生の合格者が極めて少ないケースがあります。これは必ずしも不正な選考が行われているわけではなく、面接や小論文の評価において、若い受験生の方が伸びしろがあると判断される傾向があるためと考えられています。
一方で、再受験生を積極的に受け入れている大学も存在します。こうした大学では、多様なバックグラウンドを持つ学生を歓迎し、実際に20代後半から30代、時には40代の合格者も出ています。志望校を選ぶ際には、過去の合格者の年齢構成を調べることが非常に重要です。
また、面接試験の有無や配点も大学によって異なります。面接の比重が高い大学では、年齢や経歴が合否に影響しやすい傾向があります。逆に、学力試験の配点が高く面接が参考程度の大学では、純粋な学力勝負となりやすいでしょう。
再受験生に寛容な大学を選ぶことは、合格可能性を高めるための重要な戦略です。自分の年齢や経歴を考慮し、受け入れられやすい大学を中心に受験することが賢明といえます。
6年間の学生生活を送ることになる
再受験で医学部に合格した場合、1年次から入学するため卒業まで6年間かかります。これは学士編入と比べて長い期間であり、年齢を重ねた再受験生にとっては重要な考慮事項となります。
30歳で医学部に入学した場合、卒業時には36歳になります。その後の初期研修が2年間あるため、一人前の医師として専門的な診療を始められるのは38歳以降となります。医師としてのキャリアを積む時間が、若い医師と比べて限られることは事実です。
また、6年間という長い学生生活は、経済的な負担も大きくなります。国公立大学でも授業料は年間約54万円であり、6年間で約320万円かかります。私立大学なら総額で2000万円から3000万円以上かかることもあります。この期間の生活費も含めると、相当な経済的準備が必要です。
一方で、6年間かけてじっくり学べることはメリットでもあります。基礎医学から臨床医学まで体系的に学び、実習を通じて確実にスキルを身につけることができます。学士編入のように途中から入って追いつく苦労がなく、クラスメートと同じペースで学習を進められます。
また、1年次から入学することで、同級生との人間関係をしっかり築けます。6年間を共に過ごす仲間は、医師になってからも貴重なネットワークとなります。時間をかけてでも、確実な基礎を築きたいという方には、再受験が適しているといえるでしょう。
学士編入の特徴
学士編入とは、四年制大学を卒業した者を対象に、医学部の2年次または3年次に編入する制度です。社会人経験者や他分野の専門知識を持つ人材を医学部に受け入れることを目的としています。
学士編入には独特の特徴があり、再受験とは大きく異なる点が多くあります。ここでは、学士編入の主要な特徴を5つ解説します。
- 試験科目が絞られ理系科目中心の学習となる
- 実施している大学が限定される
- 募集人数が少なく競争率が非常に高い
- 卒業までの期間が短縮される
- 社会人経験が評価されやすい
試験科目が絞られ理系科目中心の学習となる
学士編入の大きな魅力は、試験科目が一般入試よりも少なく、特に数学が不要な大学が多いことです。多くの大学では、英語、生命科学系の科目、面接、小論文が主な試験内容となっています。
生命科学系の試験では、生物学、生化学、分子生物学、生理学などの知識が問われます。高校生物の範囲を超えた大学レベルの内容が出題されるため、専門的な勉強が必要ですが、範囲が絞られている分、集中して学習できます。文系出身者にとっても、理系科目が生物系に限定されるため、物理や化学を避けられる可能性があります。
英語は医学論文や科学論文を読む能力が試されます。一般的な英語力に加えて、医学英語や科学英語の語彙を習得する必要があります。ただし、社会人として仕事で英語を使っていた方や、大学で英語をしっかり学んだ方にとっては、有利に働くことが多いでしょう。
数学が不要であることは、特に文系出身者や、長く数学から離れていた社会人にとって大きなメリットです。一般入試では数学三まで必要な大学が多く、この学習だけでも膨大な時間がかかります。学士編入なら、その時間を生命科学の学習に集中できます。
ただし、大学によって試験科目は異なります。物理や化学が出題される大学もあれば、独自の総合問題を課す大学もあります。志望校の過去問を早めに確認し、必要な科目を把握することが重要です。
実施している大学が限定される
学士編入の大きな制約は、実施している大学が限られており、選択肢が狭いことです。国公立大学では約20校から30校程度、私立大学では数校しか学士編入を実施していません。
実施大学の中には、地理的に通いにくい場所にある大学もあります。家族がいる方や、特定の地域で医療活動をしたい方にとって、選択肢が限られることは大きなデメリットとなります。また、各大学の教育方針や研究分野も異なるため、自分の希望に合った大学が学士編入を実施しているとは限りません。
さらに、学士編入を実施している大学でも、毎年募集があるとは限りません。年度によっては募集を停止したり、募集人数を変更したりすることもあります。受験を計画する際には、最新の募集要項を必ず確認する必要があります。
また、学士編入の試験日程は大学によって異なりますが、多くは夏から秋にかけて実施されます。一般入試のように複数の大学を併願することは可能ですが、試験日が重なることもあり、実際に受験できる大学数は限られます。
このように、学士編入は一般入試に比べて受験機会が少ないため、不合格だった場合のリスクも高くなります。学士編入だけに絞るのではなく、一般入試も視野に入れた併願戦略を立てることが賢明です。
募集人数が少なく競争率が非常に高い
学士編入の最大の難関は、募集人数が極めて少なく、競争率が非常に高いことです。多くの大学では、学士編入の募集人数は数名から十数名程度であり、一般入試の募集人数とは桁違いに少なくなっています。
たとえば、一般入試で100名近くを募集している大学でも、学士編入では5名しか募集しないというケースがあります。それに対して、全国から優秀な大学卒業者や社会人が応募するため、競争率は10倍から50倍、時には100倍を超えることもあります。
高い競争率は、合格の難易度を大きく上げます。学力が十分にあっても、倍率が高ければ運の要素も大きくなります。また、面接の評価が合否を左右することも多く、学力だけでなく人物評価も重要になります。
さらに、学士編入の受験生は、すでに大学を卒業している優秀な人材ばかりです。研究者として実績がある人、医療関連の資格を持っている人、海外経験が豊富な人など、多様で高いレベルの受験生と競争することになります。
このような厳しい競争を勝ち抜くには、単に試験で高得点を取るだけでなく、なぜ医師を目指すのかという強い動機と、それを説得力を持って伝える力が必要です。学士編入は狭き門であることを理解したうえで、十分な準備をして臨む必要があります。
卒業までの期間が短縮される
学士編入の大きなメリットは、2年次または3年次から入学するため、卒業までの期間が短くなることです。一般入試で1年次から入学すると6年かかりますが、学士編入なら4年から5年で卒業できます。
年齢を重ねた社会人にとって、この時間短縮は非常に大きな意味を持ちます。たとえば30歳で学士編入に合格し2年次に編入した場合、34歳で卒業できます。一般入試で1年次から入学すると36歳での卒業となるため、2年の差が生まれます。この2年間は、医師としてのキャリアを積む貴重な時間となります。
経済面でも、在学期間が短い分、学費や生活費の総額が少なくなります。国公立大学なら約100万円以上、私立大学ならさらに大きな金額を節約できます。また、早く医師として働き始められることで、収入を得る時期も早まります。
ただし、編入後のカリキュラムは決して楽ではありません。1年次の内容を独学で補いながら、2年次または3年次の授業についていく必要があります。解剖学や生理学など、医学の基礎をしっかり理解していないと、後々の学習に支障が出ることもあります。
それでも、時間を有効活用したい方や、できるだけ早く医師になりたい方にとって、学士編入の期間短縮は大きな魅力です。短期集中で医学を学び、効率的に医師への道を進めることができます。
社会人経験が評価されやすい
学士編入では、これまでの社会人経験や専門知識が面接や小論文で評価の対象となります。一般入試では学力が最優先されますが、学士編入では多様なバックグラウンドを持つ人材を求める傾向があります。
たとえば、企業で働いていた経験、研究者としての実績、医療関連職での経験、ボランティア活動、海外での活動など、様々な経験が医師としての資質を示す材料となります。なぜ今医師を目指すのかという問いに対して、具体的な経験に基づいた説得力のある回答ができれば、高く評価されます。
また、特定分野の専門知識を持っていることもアドバンテージになります。理学部や工学部で学んだ知識は、医学研究や医療技術の発展に貢献できます。文学部や法学部で学んだ知識は、医療倫理や医療制度の理解に役立ちます。多様な視点を持つ医師が増えることは、医療界全体にとってもプラスです。
面接では、これまでの経験をどう医療に活かすか、どんな医師になりたいかを具体的に語ることが重要です。単に「人を助けたい」という漠然とした動機ではなく、自分の経験から得た問題意識や、実現したい医療の形を明確に示せれば、面接官の印象に残ります。
このように、学士編入は年齢や経歴をハンディキャップではなく、強みとして活かせる制度です。社会人としての経験に自信がある方には、学士編入が適した選択肢といえるでしょう。
社会人や卒業見込みではどちら選ぶべきか
再受験と学士編入、どちらを選ぶべきかは、個人の状況や能力、目標によって異なります。一概にどちらが良いとは言えませんが、いくつかの判断基準を参考にすることで、自分に適した選択ができます。
ここでは、どのような条件の人にどちらが向いているのかを具体的に解説します。
数学が苦手で理科は生物が得意であれば再受験があっている
数学に強い苦手意識があり、特に微積分などの高度な内容に自信がない方には、学士編入が向いています。一般入試では数学三までが必須となる大学が多く、この学習だけでも膨大な時間がかかります。
数学は積み重ねの学問であり、基礎が抜けていると応用問題が全く解けません。社会人として長く数学から離れていた場合、中学レベルから復習する必要があることもあります。文系出身者にとっては、特に高い壁となるでしょう。
一方、生物が得意な方は、学士編入で有利に戦えます。学士編入の試験では生命科学が中心となるため、生物の知識がベースにあれば、大学レベルの内容も比較的スムーズに習得できます。高校生物で高得点を取っていた方や、生物系の学部を卒業した方には特におすすめです。
ただし、学士編入でも一部の大学では物理や化学が出題されることがあります。また、英語は必須であり、医学英語のレベルも高いため、英語が極端に苦手な場合は厳しいでしょう。得意科目と苦手科目のバランスを冷静に分析し、どちらが自分の強みを活かせるかを判断することが重要です。
また、学士編入は募集人数が少なく競争率が高いため、不合格のリスクも高くなります。学士編入だけに絞るのではなく、一般入試も並行して準備するという戦略も検討する価値があります。
時間をかけてでも確実に基礎から学びたい場合は学士編入を検討
医学の基礎からしっかり学びたい、時間をかけてでも確実に知識を身につけたいという方には、再受験が向いています。1年次から入学することで、解剖学、生理学、生化学といった基礎医学を体系的に学べます。
学士編入で2年次や3年次から入学すると、1年次の内容を独学で補う必要があります。大学によっては補講や補習が用意されていますが、それでも他の学生が1年かけて学んだ内容を短期間で習得するのは容易ではありません。
また、1年次から入学することで、同級生との人間関係をゆっくり築けます。6年間を共に過ごす仲間は、学生生活だけでなく、医師になってからも重要なネットワークとなります。学士編入で途中から入ると、すでに出来上がっているクラスの輪に入っていく必要があり、人によっては孤独を感じることもあります。
一方で、6年間という長い期間は、年齢的にも経済的にも負担が大きくなります。30代で入学した場合、卒業時には30代後半となり、医師としてのキャリアを積む時間が限られます。また、6年分の学費と生活費は相当な金額になります。
時間と経済に余裕があり、じっくりと医学を学びたいという方には再受験が適しています。逆に、できるだけ早く医師になりたい、効率的にキャリアを進めたいという方には、学士編入の方が合理的でしょう。
細かい条件や状況によってもどちらを選ぶべきかは異なる
再受験と学士編入のどちらを選ぶかは、年齢、経済状況、家庭環境、現在の学力、目指す医療の形など、様々な要素を総合的に判断する必要があります。単純にどちらが良いとは言えません。
たとえば、20代前半で大学を卒業したばかりの方と、30代後半で家族がいる方では、最適な選択が異なります。若い方は時間に余裕があるため、6年間かけて再受験する選択もありです。一方、年齢が高い方は、少しでも早く医師になれる学士編入の方が現実的かもしれません。
経済面でも状況は人それぞれです。十分な貯蓄がある方、家族の経済的支援が得られる方は、学費の総額が高くなる再受験でも問題ありません。一方、経済的に厳しい方は、在学期間が短い学士編入を選ぶことで負担を軽減できます。
また、志望する医療の分野によっても選択が変わります。研究医を目指す方は、基礎医学をしっかり学べる再受験の方が向いているかもしれません。臨床医として早く現場に出たい方は、学士編入で効率的に進む方が良いでしょう。
両方の可能性を並行して準備することも一つの戦略です。学士編入の試験は夏から秋にかけて実施されるため、その結果を見てから一般入試の出願を決めることもできます。柔軟な姿勢で、複数の選択肢を用意しておくことが、合格への近道となります。
まとめ
医学部を目指す際、再受験と学士編入という2つの道があり、それぞれに特徴があります。再受験は高校範囲全体の学習が必要ですが、すべての医学部が選択肢となり、6年間かけて基礎からしっかり学べます。学士編入は試験科目が絞られ期間も短縮されますが、募集人数が少なく競争率が非常に高いという特徴があります。
どちらを選ぶべきかは、数学の得意不得意、年齢、経済状況、学びたい内容など、個人の状況によって異なります。数学が苦手で生物が得意な方は学士編入、時間をかけて基礎から学びたい方は再受験が向いています。ただし、細かい条件によっても最適な選択は変わるため、自分の状況を冷静に分析することが重要です。
両方の選択肢を理解し、場合によっては併願することも検討しながら、自分にとって最良の道を選択しましょう。十分な準備と明確な目標があれば、どちらの道を選んでも医学部合格という目標は実現可能です。
監修者情報
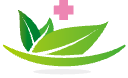
医学部専門予備校
メディカルフォレスト
運営部
メディカルフォレストは、医学部合格をめざす受験生に向けて「完全定員制」「少人数教育」「個別最適な学習プラン」を展開する医学部専門予備校です。
基幹6科目において豊富な合格実績を持った講師陣が、生徒一人ひとりと信頼関係を築きながら、データに基づく戦略的指導をおこなっております。