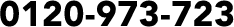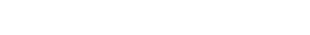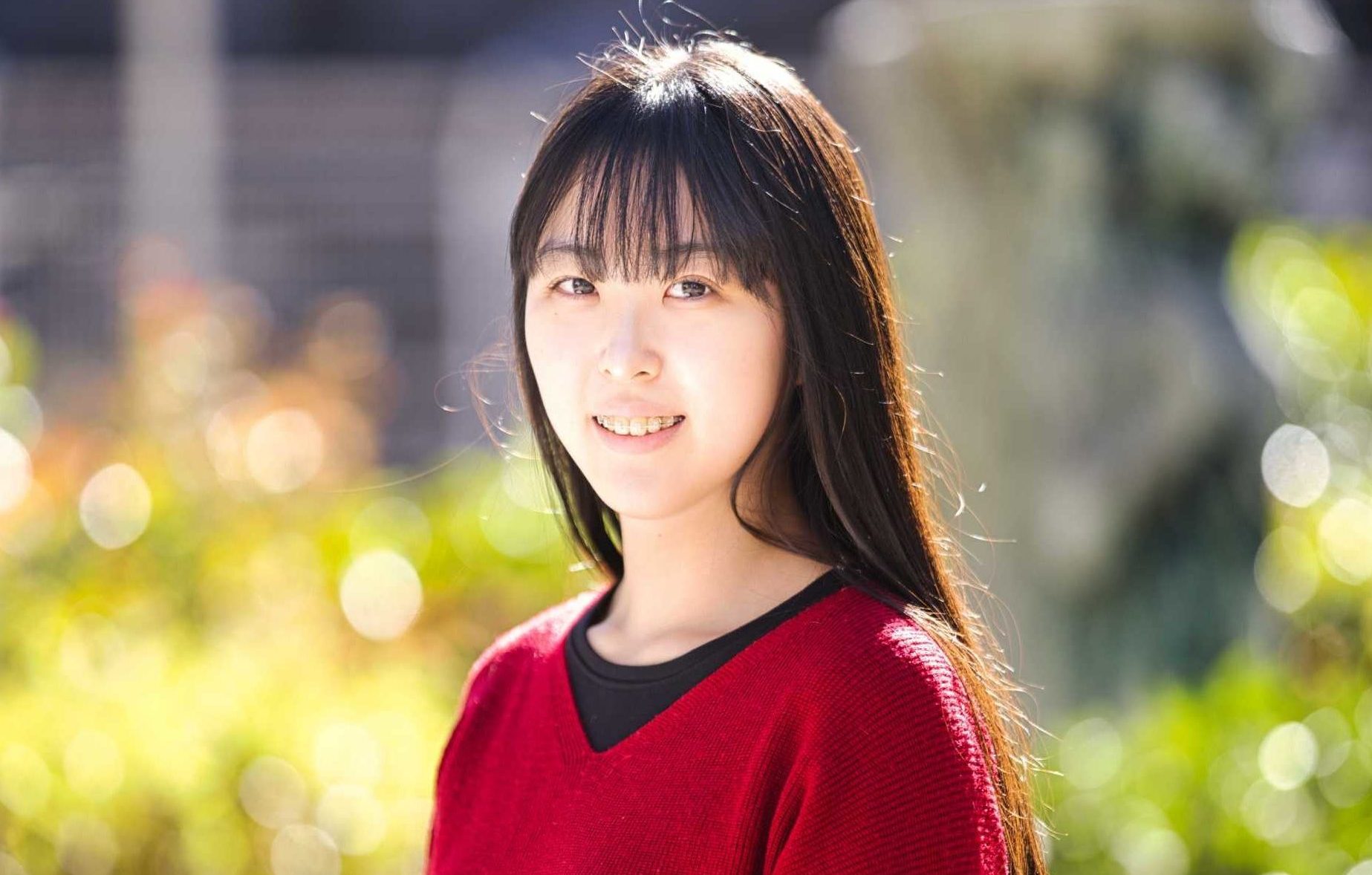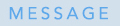合格者の声

計画的な学習と自分に合った息抜き
フォレストで過ごした充実の1年間
東海大学医学部医学科 一般選抜
はじめに
私が受験勉強を本格的に始めたのは高3の夏頃です。それまでは大手集団塾には通っていましたが、部活と遊び中心でまともに勉強はしておらず、学校での席次もビリのあたりをうろちょろとしていました。
6月に部活を引退し、それから本格的に受験勉強を始めたのですが、勉強の仕方すらまともに定まっておらず、計画性もなく、ただ気分に任せて勉強をしていたため、全く成績は伸びることはなく、現役時の河合塾の偏差値は散々なもので救いようのない成績だったため、当然1校も1次を突破することなく浪人が決まりました。
そうしてまず1浪目では大手医学部専門予備校にて基本的な内容を学習し、2浪目でメディカルフォレストに入って、ようやく成績を伸ばすことが出来たという感じです。2浪目を迎え、果たして翌年の受験で合格できるのか?という先の見えない不安感に苛まれましたが、特に重要と感じたことは「ストレス対処法」と「夏場のモチベーションの維持」です。
浪人期間をノンストレスで切り抜けることはまず出来ませんので、ストレスと上手に付き合っていく必要があります。私の場合、ストレス発散になっていたことは主に2つあり、それは「友人と話すこと」と「散歩をすること」です。「浪人生になったのだから、一切友人を作らない」というスタンスも良いと思いますし、実際に私もそうしようとしていました。しかし、浪人の1年間は短いようで長いです。その1年間、一切友人を作らずに乗り切るのは中々に苦しいです。そのため友人を作り、勉強について話したり、愚痴を吐いたり、勉強とは全く関係のないような話をしたりすることで、重たい気分も軽くなりますし、お互いに刺激し合えてモチベーションも高まります。是非、1人でもいいので友人をつくることをオススメします。今でもフォレストで知り合った友人たちにほ感謝の気持ちでいっぱいです。また浪人中は、当然朝から晩まで屋内にいます。人にもよるとは思いますが、私は1日中屋内にいると気が滅入ってしまうので、毎日休憩と運動がてら散歩をしていました。外の空気に触れて、町を眺めるだけで憂鬱な気持ちも少しは晴れます。そのため、私はこの1年でかなり大塚周辺には詳しくなりました(笑)。また、これは個人的な趣味になってしまうのですが、ラジオを聞くこともストレス対処法として良いと思います。浪人期間中、笑うことはそう多くはないですから、散歩をしながら芸人のラジオを聞いて、クスクス笑うと辛さも吹き飛びますよ。
一番苦労したことは、夏の間のモチベーションの維持です。秋からは入試も近くなってきますし、過去問も始めるのでモチベーションを維持しやすいのですが、7 ~8月はまだまだ入試本番まで長く感じてしまうので中弛みします。
さらに通塾時の物凄い暑さで、心も体も本当に疲れます。このモチベーションが低くなってしまっている時期に大事なのは、逆にモチベーションに頼って勉強しないことだと思います。私の場合、もう「勉強マシーン」になった気持ちで勉強しました。また、こういった時こそ先程も挙げた友人の存在が励みになります。「受かったら何をしたいか」やくだらない話を友人と話して、乗り越えられました。
フォレストでの勉強法
10月頃までは、通常の集団授業+週1での英数化の個別授業
1 1月頃からは、直前講習+週1での英数物化の個別授業をとっていました。
それでは私が行っていた各科目の勉強を紹介します。
数学
テキストと、高平先生の個別授業でのプリントをメインに使用していました。
私の場合は、集団授業のテキストは難しく感じたので、集団授業で発展内容、個別授業で基礎~標準レベルの問題を演習しました。
高平先生のプリントやテキストは、根本的に分かっていないと解けない問題が多いので、実力を底上げしてくれました。
また計算力をつけるために、「合格る計算シリーズ」を毎朝出来る限りやるようにしていました。特に数3の微分積分の計算に関しては、私の場合は触れていないと出来なくなってしまうので定期的に「合格る計算シリーズ」で復習するようにしていました。
基礎の復習としては、個別授業のプリントに加え「入門/基礎問題精講」を使用しました。「入門/基礎問題精講」は基本事項がある程度網羅されており、その上問題数が少ないので周回しやすくオススメです。
フォーカスゴールドや青チャートは網羅度が非常に高く良いとは思うのですが、とにかく問題数が多く周回しづらいので、数学が苦手な人はフォーカスや青チャートにこだわらず、「入門/基礎問題精講」で基礎を固めた方が良いと思います。
英語
知識系は石丸先生が授業中に板書した知識集や、海藤先生の熟語/単語/医系単語プリントをとにかく周回しました。
石丸先生の知識集では、同意義の熟語、単語、構文をまとめて板書して下さるので覚えやすかったですし、同意義語/構文を連想出来るようになりました。
海藤先生の知識プリントには、数は控えめに厳選された頻出単語が載っているので、それをやるだけで大分伸びますし、めちゃくちやタイムパフォーマンスが良かったです。
文法はテキストや授業で用いたプリントをメインで使用していました。また、「Vintage」も授業と併用して使用し、知識を定着させました。
長文は授業や個別で使ったプリントを復習し、和訳の仕方が分からない文はとにかく先生に質問しました。
また、私は雰囲気で長文を読んでしまう癖があり、それが原因で過去問での点数がイマイチ伸びなかったので、論理的に文を解説してくれる英文解釈クラシックという参考書を秋から使用し、最後の最後まで何度も復習し論理的に文を読む癖をつけるよう心がけました。
物理
テキストに基礎~発展までの典型問題が載っており、網羅度が高いので、テキストをやり込めば大丈夫だと思います。
また竹川先生と古宮先生が配ってくださる演習プリントでは、初見では解きにくく珍しい問題なども扱うので、そちらも復習するようにしていました。
また、私の場合は基礎に不安があったので、「漆原晃の物理が面白いほどわかるシリーズ」と「良問の風」もとにかく直前期まで周回し、片っ端から基礎の穴を埋めるようにしていました。
特に「漆原晃の物理が面白いほどわかるシリーズ」は一から解説してくれる上に、典型問題までカバーしているので、かなりオススメです。
苦手な分野は、このシリーズで基礎から固めると良いと思います。
一方で得意な分野に関しては「名門の森」なども部分的に使用して強化しました。
化学
とにかく吉野先生のプリントとテキストを使えば良いと思います。問題数は控えめな割に網羅度が非常に高いので、めちゃくちゃ効率がいいです。
私は化学が一番の苦手科目で、特に無機有機に関しては1浪目では定着できず、2浪目でありながらもほぼ初見という状態でした。
それでも、とにかくプリントとテキストをやり込んだことで伸びたので、むやみに他の参考書には手を出さず、プリントとテキストをやり込むことをオススメします。
また無機有機の知識は、秋以降に毎晩帰宅後の30分~1時間で反復して復習し、定着させるよう心がけました。
個別授業では、吉野先生に最初の10分ほど知識確認をして頂くことが恒例でした。
また苦手分野の演習や過去問で分からなかったところを質問していました。
小論、面接
週1の2次対策授業以外では、特に自分ではやりませんでした。一方で入試が始まってからは、柴田先生には二次対策についてお世話になりっぱなしでした。自分でも受験した多くの学校で一次通過になるとは考えておらず、すべての学校において十分な準備をしていたわけではありませんでした。しかしいざ入試が始まり、連日のように柴田先生に二次対策のご指導を頂き、各学校に合わせて至らない点を改善していくことで自信を持って小論面接に臨むことができました。柴田先生は休日にも関わらず、LINEでの質問対応や、対策資料や予想される面接での質問の資料を作って送ってくださり、直前まで対策することができました。
過去問について
10月頃から徐々に過去問を解き始めました。特に私立医学部を受験する場合、10校近くの過去問を2~3年分解くことになるかと思います。無計画にやっていては、直前期にやるべき過去問がまだ残っている…ということにもなりかねないので、計画を立てた上で過去問演習を進めていくことをオススメします。(私の場合、10月からは最低でも1日1科目はやるようにしていました。)
しかし、入試で最も重要なことは過去問演習ではなく基礎の復習です!私立医学部の問題の場合、下位~中堅ぐらいまでなら、基礎的/典型的な問題が大半だと思います。なので、直前期に過去問だけをやっていて基礎が抜けてしまうということが最も避けなくてはならないことです。そのため、計画的に少しずつ過去問を進めながら、並行して基礎の復習をするといいと思います。また、極論を言ってしまえば過去問をやらなくても何とかなったりします。私の場合、過去問を全くやらなかった学校が受かったりもしました。そのため、直前期も受験期も基礎の復習を優先しましよう。
また過去問の出来不出来で落ち込む必要は全く無いです。実際に、私の場合は過去問では何年も合格レベルの点数を取れていた学校が本番では思うようにいかず、逆に相性が悪く過去問の点数も足りていなかった学校で複数合格をいただきました。本当に受験結果は過去問通りになるとは限りません。私はかなり過去問の出来不出来で一喜一憂してしまっていたので、今思えば本当に時間を無駄にしてしまったなと思います。
模試を受けたら、可能な限りその日のうちに復習し弱点を洗い出しました。また模試(過去問)で出来なかった問題や授業の演習で出来なかった問題を集めたノートを作ることをオススメします。すぐに復習出来ますし、直前期にこれさえ見ておけば大丈夫というノートを作っておくと、気持ち的に楽になります。
また模試の結果には、どうしても一喜一憂してしまうと思います。ですが、大事なのは感情的になるのではなく、失敗した原因を分析し、対策して次に活かすことです。落ち込むなと言われても無理なので落ち込んでも良いのですが、しっかり分析して、「どういうミスが多いのか」「どういった時にミスをしてしまうのか」「それはどうしたら防げるのか」等を書いたノートを作るといいと思います。
またフォレストでは模試の度に、科目別と総合での上位5名が貼り出されます。私は常に、総合で5位以内をキープすることを意識していました。この貼り出しは闘争心が掻き立てられてモチベーションに繋がり本当に良かったです。
フォレストでの生活、フォレストの良かったところ
11月までは7時間ほど睡眠時間をとっていました。何度か睡眠時間を減らそうと試みたのですが、どうしても続かなかったので諦めました(笑)。12月以降の直前期は、睡眠時間は6時間ほどにし、また入試本番の時間に合わせて、早寝早起きをし始めました。焦って睡眠時間を減らしても結局効率が悪いので、やはり最低6時間はとったほうが良いと思います。フォレストでは、月~土まで授業がありますが、どの授業においてもそれなりの量の宿題が出ると思います。それらの宿題は出来る限り土曜日までに8割方終わらせるようにし、日曜日は残った宿題と前の週の復習をしていました(出来ないことも多かったですが……)。
集団授業、個別授業、学校別対策授業で多くの先生に教わりましたが、どの先生も質問に快く受け答えくださり、質問が非常にしやすかったです。授業中にギャグを連発するような先生もいらっしやって、楽しく授業も受けられました。フォレストの授業の特徴として、よく当てられるということがあります。そのため、皆がどれくらい自分よりも出来ているのかが把握できます。私は当てられても答えられない場合が多かったので悔しい思いを沢山しましたが、それゆえに闘争心も芽生え、モチベーションの維持にも繋がりました。ですが、当てられるのが苦手という方もいると思います。私も実際当てられるのが苦手なのですが、授業のメンバーはずっと同じなため、そのうち慣れてくるのであまり気にする必要はないと思います。
スタッフの方々にも本当にお世話になりました。友人に受験勉強の悩みや愚痴を吐くこともありましたが、スタッフの方々も悩みや愚痴をよく聞いて下さりました。
フォレストには、週1回のコーチングがあるので、自分から足を運ばなくても悩みを打ち明ける場が用意されており、これも本当に良かったと思います。望月さんや小島先生には、勉強計画や成績などについて、大内さんにはストレス対処法や睡眠の質を上げるにはどうすれば良いのか等の生活関連についてよく相談に乗っていただきました。コーチングの度にアドバイスをして下さり、精神的に本当に助かりました。
また、私は夕食をフォレストの食堂でとっていたのですが、食堂の方にもよく応援の言葉をかけていただき、本当に心の励みになりました。
最後のメッセージ
私は東海大学医学部に合格した後、第1志望だった大学の後期試験も受験しました。2次試験まで進んだものの惜しくも補欠という結果で、繰り上がることはありませんでした。手応えもあったので、合否を見たとき、「あと1問合っていれば~」という悔しさが込み上げ涙しました。この悔しさは今でも心に残っていますが、それと同時に「後期までやり切った」という実感もありました。 こまでやり切る力を付けてくださったフォレストの先生方やサポートしてくださったスタッフの方々には感謝の気持ちでいつばいです。
この1年間はやはり大変でしたし、心身共にキツかったのですが、今思い返すとフォレストでの日々は本当に充実した濃い1年間で、受験が終わってから数週間は受験ロスになってしまいました(笑)。現在通学時に電車で大塚駅を通るのですが、大塚駅を通る度にいつもフォレストの建物を見つけてはホッコリした気持ちになっています(笑)。
1年間は長いようで短いですが、短いようでやっぱり長いです。時には上手くいかず、全てを投げ出したくなる時もあると思います。
そんな時はスタッフの方々や友人と話をしたり、散歩をしたりして苦労と上手く付き合っていきましよう。
とにかく勉強を継続することが大事です。受験生の皆さんは後悔のないよう1日1日を大切にして、やりきって欲しいです。
頑張って下さい!