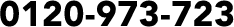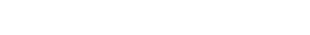医学部受験における生物の学習で大切なポイントとは?合格点に乗せるための超メソッド
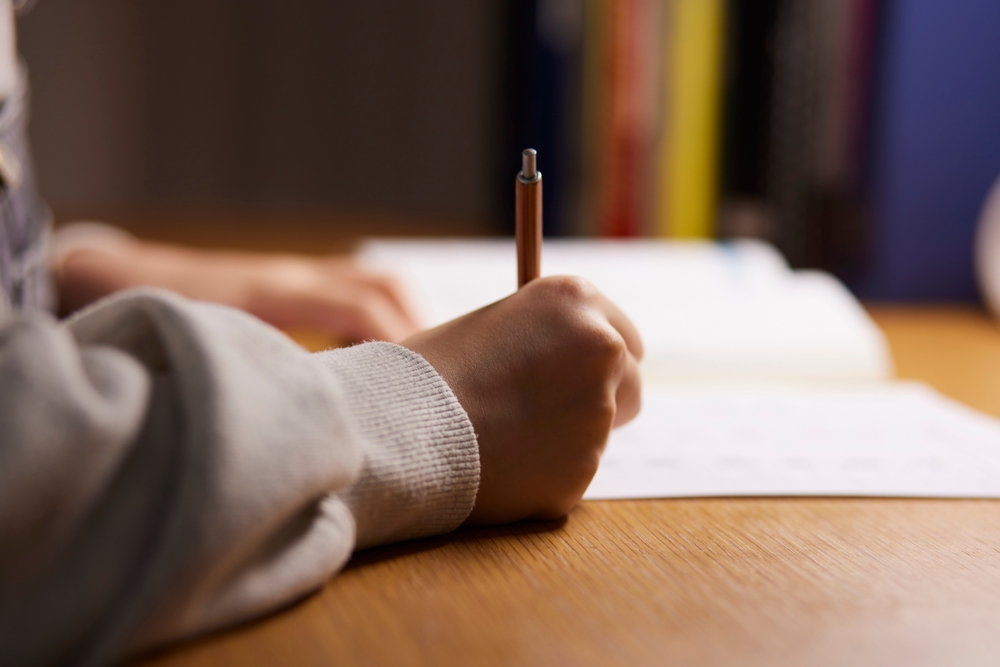
生物の学習で大切なポイント
生物は平均点がとりやすい科目です。しかし、高得点をとることが難しい科目でもあります。暗記科目だと思われがちな生物ですが、暗記をひたすら頑張れば、短期間で一発高得点を狙える科目ではありません。
- 骨格を作ってから肉付けしていく
- 他の分野とのつながりを見つける
- 日本語を正しく読み、正しく書く
実は、積み重ねがとても重要な科目なのです。他分野間とのつながりが見えてきて初めて、平均点から一つ抜けた得点をすることができるのです。また、高得点を取れるようになると、比較的安定して、高得点を取り続けることができる科目でもあります。受験生にとって、大きな武器になりうる科目です。生物を大きな武器にするための学習方法について、考えてみましょう。
①骨格を作ってから肉付けしていく
生物の学習は、暗記を先にするのではなく、全体像を把握することから始めましょう。たとえば、呼吸のしくみについて理解するときに、「解糖系」「クエン酸回路」「電子伝達系」の反応式や、反応過程の物質から覚えようとしても、よほど暗記が得意な人でなければ難しいでしょう。
しかし、グルコースからエネルギーを取り出す過程であるという大筋を理解し、そのエネルギーがどのように取り出されているのかに注目すると、水素の動きがとても重要であることがわかります。
このように、まずは、現象の全体像を見てイメージをつかみ、大きな骨組みを作って、それから用語の知識などを付けたしていきましょう。用語を忘れることがあっても、一度つかんだイメージは、忘れにくいものです。
②他の分野とのつながりを見つける
生物の学習は、成績上位層になればなるほど、他の分野との結びつきが、とても重要になってきます。生物で取り扱う内容は、分野ごとに分けられていますが、一歩引いて考えると、「一つの生命体の中で起こっている現象」や、「一つの生態系の中で起こっている現象」についての学問であることが見えてきます。
生体内で起こる化学反応は様々ですが、その多くに「酵素」が関与しています。酵素は「遺伝子」の発現によって合成されます。この発現する遺伝子の違いによって、同個体・同遺伝子での細胞でも働きの違う「細胞・組織・器官」となり、動物の生体内で、「免疫系」・「神経系」・「内分泌系」など、様々な役割を与えられます。分野にとらわれた学習では、生物全体の学習の意義を見失ってしまうことが多くなります。
他分野とのつながりをみつけることは、生体で起こっている現象が起こる原因や、その現象の意味を理解するのに必要です。そして、現象の原因・意味を理解することができると、生物全体の理解度がぐっと高くなります。
③日本語を正しく読み、正しく書く
生物の用語には、定義があります。考察問題は、特に日本語力が必要になります。日本語をしっかり読み、分析する力、また、読み手に正しく伝わる文章を書く力が不可欠です。
生物の実験問題では、初見の内容が取り扱われることが多いです。その際、初めて見た単語に惑わされず、そのしくみを読み取るためには、読解力が必要です。そして、問題を正しく読み取ることができれば、実験問題を考察することは、それほど難しいことではありません。一度、実験問題をじっくりと時間をかけて読んでみてください。
きちんと理解するまで読むためには、生物の知識よりも日本語力が必要であり、きちんと理解するまで読めば、問題を解答することは、難しいことではないことに気が付くことができるでしょう。
医学部受験における生物の学習が難しい理由
医学部受験で生物を選択する受験生は多いものの、実際に学習を進めていくと予想以上の難しさに直面します。暗記科目というイメージとは裏腹に、深い理解と応用力が求められる生物は、多くの受験生を苦しめる科目となっています。
本章では、医学部受験における生物学習の難しさについて、以下の4つの視点から詳しく解説していきます。
- 覚えるべき用語と知識の膨大さ
- 考察問題で問われる論理的思考力
- 実験データを正確に読み解く能力の必要性
- 最新の研究内容まで出題範囲となる現実
覚えるべき用語と知識の膨大さ
医学部の生物は、単なる暗記科目ではありませんが、それでも基礎となる知識量は膨大です。細胞の構造から始まり、代謝、遺伝、生態系まで、扱う範囲は生命現象のほぼすべてに及びます。
特に難しいのは、各分野の知識が独立しているのではなく、相互に関連し合っている点です。たとえば遺伝子の発現を理解するには、細胞内の構造や酵素の働きを知っている必要があります。また、免疫系を学ぶ際には、細胞の分化や情報伝達の仕組みも押さえておかなければなりません。
さらに医学部の入試では、教科書に載っている基本用語だけでなく、資料集や専門書レベルの詳細な知識まで問われることがあります。ホルモンの名称や働き、酵素の種類、遺伝子名など、覚えるべき専門用語は数千にも及ぶでしょう。
これらの知識をただ丸暗記するだけでは不十分で、それぞれの用語が示す現象の意味や、生命活動全体の中での位置づけまで理解する必要があります。この「量」と「質」の両方を求められる点が、生物学習の大きな壁となっているのです。
考察問題で問われる論理的思考力
近年の医学部入試では、知識を問う問題だけでなく、実験結果から法則性を見出したり、現象のメカニズムを推論したりする考察問題が増加しています。これは医師に必要な科学的思考力を測るためです。
考察問題の難しさは、初めて見る実験や現象について、既存の知識を応用して考えなければならない点にあります。たとえば、ある遺伝子を欠損させた個体の表現型から、その遺伝子の機能を推測する問題などが出題されます。このような問題では、単に暗記した知識を思い出すだけでは答えられません。
また、複数の実験結果を比較して共通点や相違点を見出し、そこから結論を導く力も求められます。実験条件の違いが結果にどう影響するかを論理的に分析し、因果関係を正しく把握する必要があるのです。
さらに厄介なのは、考察問題には明確な正解のパターンが存在しないことです。知識問題なら過去問演習で対策できますが、考察力は日頃からの訓練が必要になります。教科書の実験を丸暗記するのではなく、なぜその実験方法を選んだのか、結果から何が言えるのかを常に考える習慣が重要です。この思考プロセスを身につけるには時間がかかるため、多くの受験生が苦戦しているのです。
実験データを正確に読み解く能力の必要性
医学部の生物では、グラフや表、図表などの実験データを読み取る問題が頻出します。このデータ読解力は、知識の暗記とはまったく異なる能力であり、訓練なしには身につきません。
実験データの読み取りで求められるのは、数値やグラフの変化から生物学的な意味を正確に抽出する力です。たとえば、光合成速度と光強度の関係を示すグラフでは、曲線の傾きや飽和点の意味を理解し、それが何を示しているかを説明できなければなりません。
また、複数のグラフを比較して共通の法則性を見出したり、異なる条件下での結果を対比させたりする問題も多く出題されます。この際、グラフの軸の単位や実験条件の違いに注意を払わないと、誤った解釈をしてしまう危険性があります。
さらに難易度が高いのは、実験データに基づいて次の実験方法を提案させる問題です。これには既存のデータから何が分かっていて何が不明なのかを整理し、仮説を立てて検証方法を考える総合的な力が必要になります。
こうしたデータ読解の問題は、理系科目全般で求められる能力ですが、生物では特に複雑な生命現象を扱うため難易度が上がります。グラフを見慣れていない受験生は、まずデータの見方そのものから学ぶ必要があり、これが大きな負担となっているのです。
最新の研究内容まで出題範囲となる現実
医学部の生物で特に厄介なのは、教科書に載っていない最新の研究成果が出題される可能性があるという点です。生命科学は日々進歩しており、新しい発見や理論が次々と生まれています。
近年では、遺伝子編集技術や免疫チェックポイント阻害薬、幹細胞研究など、医療と直結する最先端の生物学トピックスが入試問題として登場しています。これらは従来の教科書には詳しく記載されていないため、受験生は科学雑誌や新聞の科学欄、専門書などから情報を集める必要があります。
ただし、最新の研究内容が出題されるといっても、完全に知らなければ解けないわけではありません。多くの場合、問題文の中に必要な情報が与えられ、それを基礎知識と組み合わせて考えることで答えられるように作られています。
しかし、日頃から科学ニュースに触れ、新しい発見の意義や原理を理解しようとする姿勢がある受験生は、こうした問題に対して明らかに有利です。最新の話題に対する興味や関心が、そのまま得点力の差となって表れるのです。
このように、固定された範囲を学習すれば済む科目ではなく、常に学び続ける姿勢が求められる点が、医学部受験の生物を難しくしている大きな要因といえるでしょう。
一番大切なこと
最後に、すべての学習に共通して言えることは、事象をビジュアル化すること、つまり、絵や図を描くことが大切であるということです。絵や図を描くためには、その事象をしっかり理解していることが必要になります。
絵や図を描くために、その事象について、詳細を自分で調べ、疑問を解決していくことが、生物に対する、より深い理解につながります。また、ビジュアル化することで、インプットだけではなく、アウトプットもしやすくなります。積極的に絵や図を描いて、より生物についての理解を深めましょう。
監修者情報
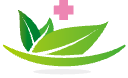
医学部専門予備校
メディカルフォレスト
運営部
メディカルフォレストは、医学部合格をめざす受験生に向けて「完全定員制」「少人数教育」「個別最適な学習プラン」を展開する医学部専門予備校です。
基幹6科目において豊富な合格実績を持った講師陣が、生徒一人ひとりと信頼関係を築きながら、データに基づく戦略的指導をおこなっております。
【特集】解説!医学部受験の基礎知識
-
 インタビュー母娘対談「家族の絆が支えた医学部受験」
インタビュー母娘対談「家族の絆が支えた医学部受験」 -
 学習計画【基礎固めが大事】医大生チューターが年間を通した学習計画の立て方や勉強法をご紹介
学習計画【基礎固めが大事】医大生チューターが年間を通した学習計画の立て方や勉強法をご紹介 -
 インタビュー一度軌道にのると、崩れない女子は強い!
インタビュー一度軌道にのると、崩れない女子は強い! -
 インタビュー自分の弱点を把握したら、あとは「反復」あるのみ
インタビュー自分の弱点を把握したら、あとは「反復」あるのみ -
 インタビュー学習計画を立てるポイント 力と自信をつけ受験合格へ
インタビュー学習計画を立てるポイント 力と自信をつけ受験合格へ -
 大学情報国立と私立医学部の難易度は違う?自分の学力に合わせた志望校の選び方
大学情報国立と私立医学部の難易度は違う?自分の学力に合わせた志望校の選び方 -
 大学情報私立医学部の偏差値は昔と今でどう変わった?
大学情報私立医学部の偏差値は昔と今でどう変わった? -
 インタビュー理数系科目克服のカギは「解き直し」にある
インタビュー理数系科目克服のカギは「解き直し」にある