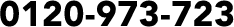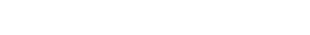医学部受験にかかる費用の種類や金額について
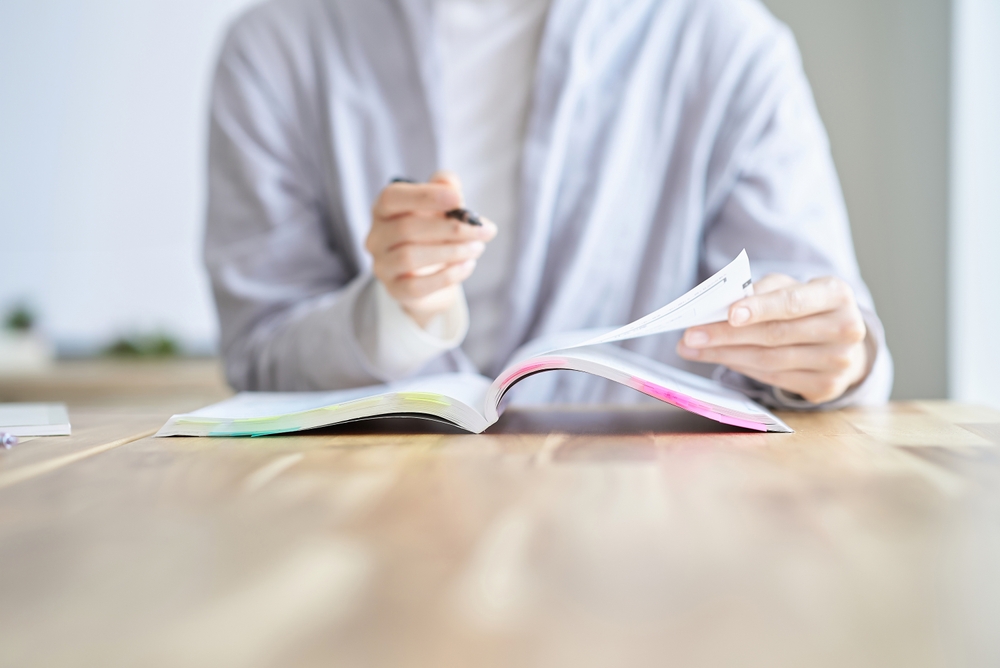
国立大学医学部の受験費用・学費
国公立大学(一般選抜・個別学力検査など)における受験料(いわゆる二次試験)は、目安として約17,000円程度となっており、ほとんどの大学でこの水準が用いられています。ただし、大学・選抜方式・日程(前期・後期)によって異なる場合もあるため、志望する大学の最新の募集要項を必ず確認してください。
また、入学金は28万2千円、年間授業料は53万5800円と定められており、6年間の総額は約350万円となります。
国立大学の学費は文部科学省の標準額によって決められているため、医学部であっても他学部と変わりません。私立大学と比較すると圧倒的に安く、経済的な負担を抑えながら医師を目指せる点が大きな魅力です。
ただし、教科書代や白衣などの教材費、実習に伴う費用、一人暮らしをする場合の生活費などは別途必要になります。それでも総合的に見れば、国立大学医学部は最も経済的に医学教育を受けられる選択肢といえるでしょう。
公立大学医学部の受験費用・学費
公立大学医学部の受験料は1万7千円で国立大学と同額です。入学金は地域内の学生が14万1千円から28万2千円程度、地域外の学生は39万3千円から56万4千円程度と、住所によって異なる設定がされています。あくまで一例ですので、大学によってはさらに高い入学金を設定している例もあると覚えておきましょう。
年間授業料は53万5800円で国立大学と同じ金額であり、6年間の総学費は入学金を含めて約350万円から400万円となります。地元出身者にとっては国立大学と同等の経済的負担で医学教育を受けられるため、大きなメリットがあります。
公立大学の特徴として、地域医療への貢献を重視する傾向があり、卒業後に一定期間地域で勤務することで返済が免除される奨学金制度を設けている大学も多く存在します。経済面だけでなく、将来のキャリアプランも含めて検討するとよいでしょう。
私立大学医学部の受験費用・学費
私立大学医学部の受験料は3万円から6万円程度で、複数回受験や複数校受験すると受験費だけでも大きな出費となります。入学金は20万円から150万円、初年度納入金は200万円から1千万円以上と大学によって大きな差があります。
6年間の総学費は最も安い大学で約2千万円、高額な大学では4千万円以上となり、平均すると3千万円前後が必要です。授業料以外にも施設設備費や実習費などが含まれるため、入学前に詳細な費用を確認することが重要です。
近年は学費を引き下げる大学や、特待生制度を充実させる大学も増えています。また、成績優秀者に対する授業料免除制度や、地域枠入試での学費減免制度を設けている大学もあるため、受験校選びの際には学費支援制度もあわせて調べることをおすすめします。
私立大学医学部の入学金・学納金ランキング
私立大学医学部の6年間総額が最も安いのは国際医療福祉大学の約1850万円で、特待生制度を利用すればさらに学費負担を軽減できます。続いて順天堂大学が約2080万円、日本医科大学が約2200万円と比較的抑えられた設定です。
中間層では東京慈恵会医科大学が約2250万円、昭和大学が約2300万円、東邦大学が約2580万円となっています。これらの大学は伝統ある医学教育と適正な学費のバランスがとれており、人気が高い傾向にあります。
高額な大学としては川崎医科大学が約4550万円、金沢医科大学が約4000万円などがあります。ただし学費が高い大学でも、教育環境や設備が充実していたり、独自の奨学金制度が整っていたりする場合があるため、総合的な判断が必要です。
入学時に利用できる奨学金や学費免除・減免制度
医学部進学時には多くの資金が必要となりますが、経済的負担を軽減するためのさまざまな制度が用意されています。ここでは主要な支援制度について、以下の項目を詳しく解説します。
- 日本学生支援機構奨学金
- 地方自治体・民間団体の奨学金
- 国の教育ローン
- 銀行などの教育ローン
- 大学独自の学費免除・減免制度
日本学生支援機構奨学金
日本学生支援機構の奨学金は、給付型と貸与型の2種類があります。給付型は返済不要で、世帯収入や成績などの条件を満たせば月額最大7万5800円が支給されます。貸与型には無利子の第一種と有利子の第二種があり、医学部生は第一種で月額最大6万4千円まで借りられます。
申し込みは高校在学中に行う予約採用と、大学入学後に行う在学採用の2つの方法があります。予約採用は進学前に採用が決まるため、資金計画が立てやすいメリットがあります。
医学部は修業年限が6年間と長いため、借入総額が大きくなりがちです。卒業後の返済計画をしっかり立てたうえで、必要な金額を適切に判断することが大切です。
地方自治体・民間団体の奨学金
都道府県や市町村が実施する地域医療奨学金は、卒業後に指定された地域で一定期間勤務することで返済が免除される制度です。貸与額は月額10万円から20万円程度で、6年間で総額1千万円以上の支援を受けられる場合もあります。
民間団体では医師会や医療関連の財団が独自の奨学金を提供しており、返済不要の給付型も存在します。企業や病院が医師確保を目的として設けている奨学金制度もあり、条件は団体によってさまざまです。
これらの奨学金は競争率が高く、成績や面接、小論文などによる選考があります。また、返済免除の条件を満たせなかった場合は一括返済を求められることもあるため、将来のキャリアプランをよく考えて利用する必要があります。
国の教育ローン
日本政策金融公庫が実施する教育一般貸付は、学生1人あたり最大450万円まで借りられる公的な融資制度です。金利は年1.95パーセント前後と比較的低く、在学中は利息のみの返済も可能なため、家計への負担を分散できます。
申し込みは保護者が行い、世帯収入の上限がありますが、医学部の場合は特例措置により条件が緩和されることもあります。審査には2週間から3週間程度かかるため、入学金や前期授業料の納入期限を考慮して早めに手続きを進めることが重要です。
日本学生支援機構の奨学金と併用できるため、両方を組み合わせることでより充実した資金計画を立てられます。ただし返済は卒業後すぐに始まるため、収入が安定するまでの期間も考慮した返済計画が必要です。
銀行などの教育ローン
民間金融機関の教育ローンは、融資限度額が500万円から3千万円と高額で、医学部の学費全額をカバーできる商品もあります。金利は年1.5パーセントから3.5パーセント程度で、金融機関や借入条件によって異なります。
審査は国の教育ローンより厳しく、保護者の収入や勤務先、信用情報などが総合的に判断されます。一方で、世帯収入の上限がなく、所得が高い家庭でも利用できる点がメリットです。また、手続きが比較的スピーディーで、急な資金需要にも対応しやすい特徴があります。
変動金利と固定金利を選べる商品が多く、長期的な返済を考えると固定金利の方が計画を立てやすいでしょう。複数の金融機関の条件を比較検討し、返済シミュレーションを十分に行ったうえで契約することをおすすめします。
大学独自の学費免除・減免制度
私立大学を中心に、特待生制度や成績優秀者への授業料免除制度を設けている大学が増えています。入試の成績上位者に対して、初年度または6年間の授業料を全額または一部免除する制度が代表的です。
地域枠入試で合格した学生に対する学費減免制度も充実しており、卒業後に指定地域で一定期間勤務することを条件に、学費が大幅に減額される場合があります。大学によっては年間100万円以上の減免が受けられることもあります。
また、在学中の成績が優秀な学生に対して授業料を免除する制度や、経済的困窮者を支援する緊急支援制度を用意している大学もあります。これらの制度は大学によって内容が大きく異なるため、志望校を決める際には学費支援制度の詳細を確認することが大切です。
受験費以外に必要な費用
医学部進学には授業料以外にもさまざまな費用が発生します。事前に把握しておくべき主な項目として、以下の費用について解説します。大学・学年・実習内容によっても変動するため、あくまで一例としてご覧ください。
- 教材費
- 実習費
- 学生寮費
- 部活動・サークル活動費
教材費
医学部では専門的な教科書や参考書の購入が必要で、1年次から年間10万円から20万円程度かかります。特に解剖学や生理学などの基礎医学の教科書は高額で、1冊あたり1万円から2万円することも珍しくありません。6年間の総額では60万円から100万円程度の教材費を見込んでおく必要があります。
実習費
白衣や聴診器などの医療用具、解剖実習での器具類、臨床実習時の移動費などが実習費として必要です。大学によっては授業料に含まれている場合もありますが、個人負担となる場合は年間5万円から15万円程度かかります。特に病院実習が本格化する高学年では、交通費や宿泊費の負担が増える傾向があります。
学生寮費
大学の学生寮を利用する場合、月額1万円から5万円程度が一般的です。食費込みの寮もあれば、自炊が必要な寮もあり、生活スタイルに応じて選択できます。民間のアパートを借りるより経済的で、同級生との交流も深まるため、多くの学生が寮生活を選んでいます。
部活動・サークル活動費
医学部の部活動は伝統的に活発で、運動部では遠征費や用具代として年間10万円から30万円かかることもあります。文化系サークルでも活動内容によっては相応の費用が必要です。ただし、部活動への参加は任意であり、経済状況に応じて選択できます。
これら以外にも、医学部受験においては交通費・宿泊費・併願校の出願料など別途必要になる費用もありますので、覚えておきましょう。
医学部の学費についてよくある質問
医学部の学費に関して受験生や保護者から寄せられる代表的な疑問について、詳しく解説します。
- 学費が改訂される可能性はある?
- 学費の納入時期と支払い方法に規定はある?
- 留年したときに学費は追加で必要になる?
学費が改訂される可能性はある?
学費は改訂される可能性があり、特に私立大学では数年ごとに見直しが行われることがあります。国立大学も文部科学省の方針により標準額が変更されれば、それに伴って学費が改定されます。
ただし、在学生の学費を遡って値上げすることは原則として行われません。入学時に提示された学費が基本的には卒業まで適用されるため、途中から大幅に負担が増えることは稀です。それでも、施設設備費などの名目で追加徴収される可能性はゼロではありません。
受験前には最新の学費情報を大学の公式サイトで確認し、不明点があれば直接問い合わせることをおすすめします。
学費の納入時期と支払い方法に規定はある?
学費の納入は前期と後期の2回に分けて行うのが一般的です。前期分は4月頃、後期分は9月から10月頃に納入期限が設定されています。入学金と初年度前期授業料は合格発表後、2週間から1か月以内に納入する必要があります。
支払い方法は銀行振込が基本ですが、口座引き落としを採用している大学も増えています。一部の大学ではクレジットカード払いや分納制度に対応している場合もあり、家計の状況に応じて選択できます。
納入期限を過ぎると除籍処分となる可能性があるため、期限管理は厳密に行う必要があります。経済的な事情で期限内の納入が難しい場合は、事前に大学の学生課に相談することで、分納や延納が認められることもあります。
留年したときに学費は追加で必要になる?
留年した場合、その学年の学費を再度納入する必要があります。国立大学では年間約54万円、私立大学では200万円から500万円程度の追加負担が発生します。医学部は進級判定が厳しく、留年率が他学部より高い傾向にあるため、注意が必要です。
大学によっては留年生向けの減額制度を設けている場合もあり、正規学費の50パーセントから70パーセント程度に抑えられることもあります。また、履修する科目数に応じた単位制の学費を採用している大学では、取得済みの単位分は免除されます。
留年を避けるためには日々の学習をしっかり積み重ねることが最も重要です。万が一留年してしまった場合でも、奨学金の継続利用や追加借入の可否を早めに確認し、学業に専念できる環境を整えることが大切です。
まとめ
医学部の学費は国公立大学で6年間約350万円、私立大学では2千万円から4千万円以上と大きな開きがあります。受験費や教材費、実習費なども含めると、さらに費用は増加します。
しかし、日本学生支援機構の奨学金、地域医療奨学金、教育ローン、大学独自の減免制度など、多様な経済支援制度が用意されています。これらを適切に組み合わせることで、経済的な負担を大幅に軽減することが可能です。
医学部受験を検討する際は、学費だけでなく利用できる支援制度も含めて総合的に判断することが重要です。早い段階から情報収集を行い、家族でしっかりと資金計画を立てることで、安心して医師への道を歩むことができるでしょう。
監修者情報
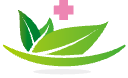
医学部専門予備校
メディカルフォレスト
運営部
メディカルフォレストは、医学部合格をめざす受験生に向けて「完全定員制」「少人数教育」「個別最適な学習プラン」を展開する医学部専門予備校です。
基幹6科目において豊富な合格実績を持った講師陣が、生徒一人ひとりと信頼関係を築きながら、データに基づく戦略的指導をおこなっております。
【特集】解説!医学部受験の基礎知識
-
 インタビュー母娘対談「家族の絆が支えた医学部受験」
インタビュー母娘対談「家族の絆が支えた医学部受験」 -
 学習計画【基礎固めが大事】医大生チューターが年間を通した学習計画の立て方や勉強法をご紹介
学習計画【基礎固めが大事】医大生チューターが年間を通した学習計画の立て方や勉強法をご紹介 -
 インタビュー一度軌道にのると、崩れない女子は強い!
インタビュー一度軌道にのると、崩れない女子は強い! -
 インタビュー自分の弱点を把握したら、あとは「反復」あるのみ
インタビュー自分の弱点を把握したら、あとは「反復」あるのみ -
 インタビュー学習計画を立てるポイント 力と自信をつけ受験合格へ
インタビュー学習計画を立てるポイント 力と自信をつけ受験合格へ -
 大学情報国立と私立医学部の難易度は違う?自分の学力に合わせた志望校の選び方
大学情報国立と私立医学部の難易度は違う?自分の学力に合わせた志望校の選び方 -
 大学情報私立医学部の偏差値は昔と今でどう変わった?
大学情報私立医学部の偏差値は昔と今でどう変わった? -
 インタビュー理数系科目克服のカギは「解き直し」にある
インタビュー理数系科目克服のカギは「解き直し」にある