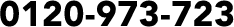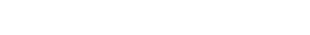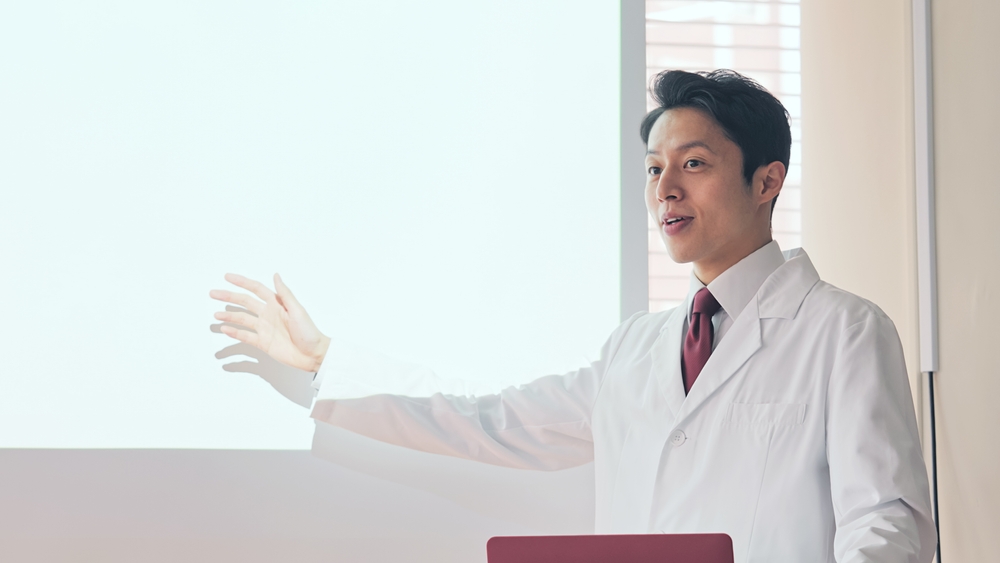医学部受験のプロが解説!年間スケジュール&学習計画との付き合い方

医学部受験において、年間スケジュールの立て方ならびに学習計画との付き合い方は、試験の合否を左右する大きな要素です。
医学部に合格するためのスケジューリングについて、医学部受験のプロが解説します。
【高1生・高2生】年間の勉強スケジュール
まずは高1生・高2生に最適な年間の勉強法スケジュールをご紹介します。
時期ごとの学習アドバイス【前期・後期】
まずは、計画を立てることから始めよう
定期テスト対策を機軸に、1週間単位のスケジュールをつくります。
場当たり的な勉強をしていると結果が出ず、モチベーションが下がりますので、具体的な目標を設定し、ひとつひとつクリアして達成感を味わうようにしましょう。
たとえば、数学なら教科書の例題や基本問題を何度も解き直す、英語なら教科書で扱った本文を10回音読する、英単語を毎日10個ずつ記憶する、国語なら教科書で扱った本文を10回音読する、漢字を毎日20個ずつ記
憶するなど。
主要3科目を最優先にしながら、学習の習慣づけを確立する
部活や学校行事とのバランスを考えながら、主要3科目(英・数・国)の勉強を最優先にして、教科書レベルの問題を完璧にマスターしてください。
机に向かって勉強する習慣を1日30分でもいいので、少しずつ続けていきましょう。
基礎固めをするには、なるべく薄い問題集を何度も繰り返すと効果的です。
また、細切れのすき間時間をうまく利用して、単語や定義などの基礎知識を定着させましょう。
推薦や国立も視野に入れた準備を
定期テストでは確実に高得点が取れるレベルまでもっていきましょう。
内申点は5段階評価で4.0以上をなんとしてでも目指してください。
現役で合格するには、まず推薦入試を利用することを考えましょう。
そのためには、定期テストで好成績を残しておく必要があります。
さらに、志望校の選択肢を最初から私立に狭めずに、まずは国立も視野に入れて士気を高めましょう。
時期ごとの学習アドバイス【夏期】
朝型のライフスタイルをキープしよう
長期の休みに入ると生活リズムが崩れやすいので、朝型のライフスタイルをキープし、学習の習慣づけを確実に行ってください。
そのためには、学習計画は前期以上に重要になります。
自分の行動を紙に書き出すことで、客観的に自分の行動を見ながら自己管理しましょう。
受験学年に備えて、主要3科目の復習を徹底的にやっておく
この約1ヵ月半は、全く勉強しない日がないように、前期で学んだ内容を総復習してください。
数学では基本公式の知識や計算力、英語では単語・文法などの知識や、教科書にあるテクストを構造的に読み解く力、国語では教科書にある評論文を構造的に読み解き、要旨を200字程度にまとめる力を磨き上げてください。
また、医学部の面接では読書についてよく質問されるので、受験学年になる前に最低でも3冊は読んでおくようにしましょう。
オープンキャンパスや医療体験ボランティアで情報収集しよう
勉強の合間を縫って、志望校のオープンキャンパスや医療体験ボランティアなどに足を運んで、パンフレットやウェブには載っていない生きた情報を集めてください。
それが医師や大学への志望動機へとつながっていきます。
また、医師体験だけではなく看護師体験にも参加すると、チーム医療に触れることができるので、開催日程をチェックしてみましょう。
医学部の面接では志望動機やボランティアについてよく質問されるので、事前に実際の現場に出向いておくと良いでしょう。
時期ごとの学習アドバイス【冬期】
テーマを絞って、集中的に弱点を補強する
1年間を通じて、苦手分野がないかを確認し、ある場合はそこに集中して勉強しましょう。
苦手分野を今のうちに克服しておかないと、受験学年になってから勉強の負担が大きくなるので注意が必要です。
共通テストの過去問にチャレンジしよう
共通テストが近いので、共通テストの過去問に挑戦してみましょう。
過去3年分の問題を時間を計って解いてみてください。まずは全科目、正答率70%が目標です。
志望校を具体的に決める
受験学年になるまえに、ある程度自分がどこに進学したいのか、目標を決めておく必要があります。
大学の入試説明会やオープンキャンパス、パンフレット、ホームページ、関係者からのお話などから情報を収集してみましょう。
行きたい大学が見つかると、ワクワクしてきて一層勉強に集中できます。
自分が心から欲するものに向けて、エネルギーを注入することができれば、きっと夢は必ず叶うはずです。
もし迷ったら、自分の心のなかで、どこに合格したいのか、いま何のための勉強しているのか、何度も自問自答してみてください。
【高3生】年間の勉強スケジュール
続いて、高3生に最適な年間の勉強法スケジュールをご紹介します。
時期ごとの学習アドバイス【前期】
まずは、計画を立てることから始めよう
受験までは長いようで短いもの。まずは自分に不足しているものを理解し、それを補うための計画を立てることが合格への第一歩となります。
我流の勉強法や解法を守っていては伸びるものも伸びません。客観的な意見を取り入れ、いかに素直な心で謙虚に現実の自分と向き合えるかが合格へのカギとなります。
年間を通して何をいつまでに何回やるのか、大まかなスケジュールを立てます。そのうえで、1週間単位のスケジュールをつくります。
高3生は学校のテスト勉強や部活、行事もあって、時間がうまく確保できないかもしれませんが、夏までには基本レベルだけでいいので、全範囲が終わるように計画しましょう。
教科書レベルの問題を完璧にマスターする
部活や学校行事とのバランスを考えながら、主要3科目(英・数・理)の勉強を最優先にして、教科書レベルの問題を完璧にマスターしてください。
基礎固めをするには、なるべく薄い問題集を何度も繰り返すと効果的です。
また、細切れのすき間時間をうまく利用して、単語や定義などの基礎知識を定着させましょう。
定期テスト対策もしっかりと
定期テストでは確実に高得点が取れるレベルまでもっていきましょう。
内申点は5段階評価で4.0以上をなんとしてでも目指してください。
推薦狙いの人は、この時期までは定期テスト対策に全力を投入してください。
時期ごとの学習アドバイス【夏期】
朝型のライフスタイルをキープしよう
長期の休みに入ると生活リズムが崩れやすいので、朝型のライフスタイルをキープし、学習の習慣づけを確実に行ってください。そのためには、学習計画は前期以上に重要になります。夏を制する者は受験を制する、と昔から言われます。自分の行動を紙に書き出すことで、客観的に自分の行動を見ながら自己管理しましょう。
穴のない勉強、それが合格者になるための必須条件
前期に抜けてしまった穴を埋める最後のチャンスなので、ここで全科目の復習を終わらせることが重要です。
ここで苦手分野が克服できなかったり、「理解と知識」の漏れが目立つと、後期からの過去問演習が思うように進まなくなるので気をつけましょう。
また、医学部の面接では読書についてよく質問されるので、最低でも1冊は読んでおくようにしましょう。
オープンキャンパスや医療体験ボランティアで情報収集しよう
勉強の合間を縫って、志望校のオープンキャンパスや医療体験ボランティアなどに足を運んで、パンフレットやウェブには載っていない生きた情報を集めてください。
それが医師や大学への志望動機へとつながっていきます。
また、医師体験だけではなく看護師体験にも参加すると、チーム医療に触れることができるので、開催日程をチェックしてみましょう。
医学部の面接では志望動機やボランティアについてよく質問されるので、事前に実際の現場に出向いておくと良いでしょう。
時期ごとの学習アドバイス【後期】
ゴールから逆算して間に合うように、計画の見直しを図る
年間スケジュールがうまく機能しているか確認しながら、そのうえで、1週間単位のスケジュールをつくっていきましょう。
そろそろ受験も見えてきます。期限までにすべての範囲を終わらせないと、合格が1年延びてしまうので注意が必要です。
一気に成績が急上昇する、それが現役生のパワー!
夏期までは分野ごとにテキストの解説を聴くこと(インプット)を通して、「理解と知識」を定着させてきました。
後期からは全範囲の問題を解くこと(アプトプット)を通して、「理解と知識」を定着させることにシフトしましょう。
このあたりから、高3生は夏期までの勉強の成果が表れ、模試の成績が急上昇しはじめます。
私立医学部向けの模試はないので、判定は気にせず、自分の勉強のペースメーカーとして利用し、復習に徹してください。
過去問を制する者が受験を制する
過去問を解くメリットは、志望大学の出題傾向を知ること、そして制限時間内で自分の現時点での実力をチェックする点にあります。
合格ラインまであと何割必要かを意識しながら、問題に取り組むことが重要です。
問題の中には、以前解いたことのあるような問題と、解いたことのない初見の問題があり、前者は典型問題なので知識で対応できますが、後者は基本原理から遡って、現場で筋道を立てて考えて突破口を見つけ出す必要があります。
過去問演習は10月くらいから取り掛かってください。
志望校上位3校までは過去5年分以上手をつけたほうが良いでしょう。
ただし、新課程の影響が大きく反映される数学は、旧課程になる前に出された問題や予想問題を中心に取り掛かってください。
時期ごとの学習アドバイス【冬期】
新しい問題より、今までやってきた問題の解き直しを
いよいよ試験本番が間近に迫ってきます。
全科目、全範囲の総復習をする際、新しい問題には手をつけず、今まで解いたことのある問題の解き直しをお勧めします。
本番での時間配分を体感しておこう
試験の1週間前になったら、時間配分が体感できるように、本番と同じ時間設定で、全科目をまとめて解いてみましょう。
実際に試験に臨んだ時のイメージトレーニングにもなります。
最後は「解けるイメージ」を頭に刷り込む
応用問題よりも、基本問題の最終チェックを高速回転で何度も繰り返し、頭の中で解けるイメージを作り上げてください。
ここまで来たら、あとは気合いです。「やればできる、絶対できる」と信じて、何度も自分に言い聞かせれば、きっとその願いは実現するはずです。
【高卒生】年間の勉強スケジュール
最後に、高卒生に最適な年間の勉強法スケジュールをご紹介します。
時期ごとの学習アドバイス【前期】
まずは、計画を立てることから始めよう
年間を通して何をいつまでに何回やるのか、大まかなスケジュールを立てます。
そのうえで、1週間単位のスケジュールをつくります。夏までには基本レベルだけでいいので、全範囲が終わるように計画しましょう。
薄めの基本書で基礎固めをする
主要3科目(英・数・理)の勉強を最優先にして、教科書レベルの問題を完璧にマスターしてください。
基礎固めをするには、なるべく薄い問題集を何度も繰り返すと効果的です。
また、細切れのすき間時間をうまく利用して、単語や定義などの基礎知識を定着させましょ
う。
とにかく受かるまでは、平身低頭な姿勢で
高卒生は受験年数によっては我流に走りやすいので、まわりの指導者に自分の癖を客観的に指摘してもらい、自分でも意識して弱点を集中的につぶしましょう。
いかに素直な心で謙虚に現実の自分と向き合えるかが合格へのカギとなります。
受かるまでは犬にでも頭を下げるつもりで、どこまでも平身低頭の姿勢で臨みましょう。
時期ごとの学習アドバイス【夏期】
前期で扱った内容の「理解と知識」を何度も繰り返す
前期は分野ごとにテキストの解説を聴くこと(インプット)を通して、「理解と知識」を定着させる学習の積み重ねが大切でした。
夏期からは前期で扱った内容をしっかり復習し、穴ができないように、全範囲の「理解と知識」を深めましょう。
年間スケジュールがうまく機能しているか確認しながら、そのうえで、1週間単位のスケジュールを調整していきましょう。
前期に扱った全科目、全範囲の復習を終わらせる
前期に抜けてしまった穴を埋める最後のチャンスなので、ここで全科目の復習を終わらせることが重要です。
ここで苦手分野が克服できなかったり、基礎知識の漏れが目立つと、後期からの過去問演習が思うように進まなくなるので気をつけましょう。
また、医学部の面接では読書についてよく質問されるので、最低でも1冊は読んでおくようにしましょう。
オープンキャンパスやボランティアにも足を運ぼう
勉強の合間を縫って、志望校のオープンキャンパスや医療体験ボランティアなどに足を運んで、パンフレットやウェブには載っていない生きた情報を集めてください。
それが医師や大学への志望動機へとつながっていきます。
また、医師体験だけではなく看護師体験にも参加すると、チーム医療に触れることができるので、開催日程をチェックしてみましょう。
医学部の面接では志望動機やボランティアについてよく質問されるので、事前に実際の現場に出向いておくと良いでしょう。
時期ごとの学習アドバイス【後期】
ゴールから逆算して間に合うように、計画の見直しを図る
年間スケジュールがうまく機能しているか確認しながら、そのうえで、1週間単位のスケジュールをつくっていきましょう。
そろそろ受験も見えてきます。期限までにすべての範囲を終わらせないと、合格が1年延びてしまうので注意が必要です。
インプットからアウトプット中心の学習へ切り替える
夏期までは分野ごとにテキストの解説を聴くこと(インプット)を通して、「理解と知識」を定着させてきました。
後期からは全範囲の問題を解くこと(アプトプット)を通して、「理解と知識」を定着させるにシフトしましょう。
高卒生にとって、理科は確実に得点源にしたいところです。
また、私立医学部向けの模試はないので、判定は気にせず、自分の勉強のペースメーカーとして利用し、復習に徹してください。
過去問を制する者が受験を制する
過去問を解くメリットは、志望大学の出題傾向を知ること、そして制限時間内で自分の現時点での実力をチェックする点にあります。
合格ラインまであと何割必要かを意識しながら、問題に取り組むことが重要です。
問題の中には、以前解いたことのあるような問題と、解いたことのない初見の問題があり、前者は典型問題なので知識で対応できますが、後者は基本原理から遡って、現場で筋道を立てて考えて突破口を見つけ出す必要があります。
過去問演習は10月くらいから取り掛かってください。志望校上位3校までは過去5年分以上手をつけたほうが良いでしょう。
ただし、新課程の影響が大きく反映される数学は、旧課程になる前に出された問題や予想問題を中心に取り掛かってください。
時期ごとの学習アドバイス【冬期】
新しい問題より、今までやってきた問題の解き直しを
いよいよ試験本番が間近に迫ってきます。
全科目、全範囲の総復習をする際、新しい問題には手をつけず、今まで解いたことのある問題の解き直しをお勧めします。
本番での時間配分を体感しておこう
試験の1週間前になったら、時間配分が体感できるように、本番と同じ時間設定で、全科目をまとめて解いてみましょう。
実際に試験に臨んだ時のイメージトレーニングにもなります。
最後は「解けるイメージ」を頭に刷り込む
応用問題よりも、基本問題の最終チェックを高速回転で何度も繰り返し、頭の中で解けるイメージを作り上げてください。
ここまで来たら、あとは気合いです。「やればできる、絶対できる」と信じて、何度も自分に言い聞かせれば、きっとその願いは実現するはずです。
科目ごとの学習アドバイス
科目ごとの学習方法を記載します。
勉強を進めるうえでの参考にしてください。
英語
『短時間でも、毎日の反復作業を続けるのが大切』
長いようで短いし、短いようで長い受験までの期間、自分の心身のコンディションと上手く付き合いながら前進していくこのチャレンジの機に自分を磨きましょう。
夏前もしくは夏半ばまでに、基礎文法事項を見直し、きちんと構文理解や文法構造で英文を処理する姿勢を作ることが先決です。
夏休み中には、それらの復習・応用と共に、受験校の過去問に改めて取り組んでみて、秋以降の勉強の方針を立てることが必要です。
秋以降は模試も忙しいですが、入試レベルの読解問題をこなしながら、反復練習を要する文法・語法や語彙のおさらいにも向かってください。
ともすると理数系科目の勉強に夢中になるあまり英語の教材を開かない日が続いた…といった事態に陥りがちですが、「一日休むと三日分穴があく」語学を侮らないように注意しましょう。
秋が深まる頃から、過去問にも本格的に取り組むことになります。
ここで注意したいのは、過去問を解く目的は点数を取ることではなく、第一にあくまで出題傾向や、自分の得手不得手を確認することにある、ということです。
夏までに固めて来た知識や技術をどう発揮することを求められているのか(文法知識はどのように問われるか、長文の長さはどの位か、記述式か選択問題か、英作はあるか…など)を確認しながら、自分に足らない学習演習を見極めていきましょう。
12月半ば以降の直前期からはより実践的に、問題への解答の速度、解く順番などを実際の入試の時間に照らし合わせて考え、本番の作戦を練っていくとよいです。
健康管理には息抜きも必要です。うまく心身のバランスをとりながら、本番にむかって調整していって下さい。
数学
『見た瞬間に解けるレベルになるまで、標準問題を繰り返す』
まずは、用語や定義の説明に注目したり、なぜこうすると問題が解けるのかを意識しながら、教科書を読んでみてください。
公式は(ごく一部を除いて)自分で証明できるようにしましょう。また、教科書を読んで少し粘ってもわからない個所があったら、予備校の先生に質問をしてください。
教科書の読み直しは、6月中には終わらせておくとよいでしょう。
それと同時に、標準的な問題集を1冊仕上げてください。難易度の高い問題集である必要はありません。
きっちり3周繰り返し、毎日最低2時間は数学に使うつもりで取り組んでみてください。
しかし、最終的にはこれでは足りないのです。
標準的な問題、パターン問題ならば見た瞬間に解法の流れがわかる。解いていくうちに次に何が起きるのか予測がついた上で解き進められる。これが医学部の数学で合格ラインを取るのに必要最低限なスキルだと思ってください。
そしてこれが応用問題を解く上でも強力な武器になります。集中的に数学に触れ、標準問題に慣れることで応用問題と対峙した際に余裕が生まれます。
「何がわかれば、どう考えれば、いつもの解法パターンにもっていけるのか」「この問題の条件だと、最終的にどんな解法の流れになりそうか」そういった思考ができるようになります。
その上で思考力を問われるタイプの問題(授業で配られる発展問題や入試問題など)をじっくりと考える練習をしましょう。
これは問題集を大体2周したら問題集と平行してやってみてください。ただ、最初は毎日のようにやる必要はありません。1週間に2~3問程度でいいと思います。
ここで大切なのはどんなにわからなくても最低15~20分程度は何も見ずに自力で考える、ということです。始めのうちは「全然わからないのに考えるのは時間の無駄だな」と思ってしまうかもしれませんが、この「自分で考える時間」というのが必要なことなのです。入試問題を解くためには、まず基礎を固めて数学に慣れてください。
パターン問題は覚えるだけでなく、理解することを意識しましょう。そのうえで解法の方針を探す、方針が間違っていそうなら戻って新たに立て直す、という練習をしてみましょう。
化学
『化学を得点源にして、ぜひ得意科目にしよう』
化学は理論分野のように公式を使って解く問題と、無機分野のように知識を問う問題に大別されます。
公式を使って解くというと数学のような難しさを感じてしまうかもしれませんが、数学とちがって図形的な考え方がほとんど必要とされません。
また、知識を問う問題についても、基本をきちんと学習していれば答えられるものです。
どちらにしても、問題集や過去問で勉強したのと同じような問題がそのまま、模試でも入試でも出題されます。そのため、化学は勉強量がそのまま実力になりやすい科目です。
まずは問題集で勉強し、それを仕上げてから過去問に取り組むようにしましょう。
無機分野や有機分野の知識は、どのようにして身につけるか自分なりの勉強法を確立していくことが重要です。
語呂合わせが載せられている参考書を使ったり、複雑な構造式を形のイメージで覚えてみたり、図録を見て印象に残すようにしたり、図を書いてノートをつくったりといった勉強の工夫が必要です。
そのうえで問題集を解くこともしましょう。とくに無機分野については、無機専用の問題集を活用すると、受験で問われる知識をおおよそすべて網羅することができます。
私立医学部入試では無機分野より有機分野のウェイトが大きく、また有機分野のうちでも合成高分子より天然高分子が頻繁に出題されます。
そして有機分野は、たんに知識が問われるばかりでなく、実際に知識を活用できるかということも、構造決定のような問題では問われます。
どのような構造式が考えられるかすべて書き出すことや条件に合う構造式をしぼることは、有機分野に特有の問題と言えます。
うまく答えが出せるようになるまで類題の練習をいとわず重ねることで上達します。
化学は得点源にしやすいので、得意科目にすることを積極的に狙っていくべきです。
夏までに問題集や過去問を解き直して、弱点を洗いだしながら、勉強不足となっている単元に取り組んでください。
分からない点を残さないでおくことが大切です。秋からは志望校のみならず、志望校と同じ難度の過去問も勉強して万全を期していきましょう。
生物
『夏までに全範囲を終わらせ、新傾向対策も忘れずに』
生物の学習は、個々の知識の暗記を先にするのではなく、全体像を把握することから始めましょう。
現象の全体像を見てイメージをつかみ、大きな骨組みを作って、それから用語の知識などを付けたしていきます。
また、成績上位層になればなるほど、他の分野との結びつきがとても重要になってきます。生物で取り扱う内容は、分野ごとに分けられていますが、一歩引いて考えると、「一つの生命体の中で起こっている現象」や「一つの生態系の中で起こっている現象」についての学問であることが見えてきます。
他分野とのつながりをみつけることは、生体で起こっている現象が起こる原因や、その現象の意味を理解するのに必要です。
問題内容の把握や考察問題は、特に日本語力が必要になります。日本語をしっかり読み、分析する力、また、読み手に正しく伝わる文章を書く力が不可欠です。
生物の実験問題では、初見の内容が取り扱われることが多いです。その際、初めて見た単語に惑わされず、そのしくみを読み取るためには、読解力が必要です。
現象の理解・読解力・説明表現のすべての学習に共通して言えることは、事象をビジュアル化すること、つまり、絵や図を描くことです。
絵や図を描くにあたり、その事象について、詳細を自分で調べ、疑問を解決していくことによって、生物に対するより深い理解につながります。
生物は、積み重ねがとても重要な科目なのです。他分野間とのつながりが見えてきて初めて、平均点から一つ抜けた得点をすることができます。
ですから、夏休みまでには全範囲を終えるようにしてください。受験生にとって、大きな武器になりうる科目ですので、コツコツ積み重ねる学習を継続してください。
教科書全体の復習として、①現象の絵や図を描いて整理する、②用語の論述説明練習を行う、この2点を早めに行い知識の理解を深め、問題に慣れていきましょう。
物理
『標準問題に絞って、解答力をしっかり身に付ける』
物理の分野は、「力学」「電磁気学」「波動」「熱力学」「原子物理」の5つに分かれていて、このなかでも特に重要なのが「力学」と「電磁気学」です。
この2つはすべての大学で確実にでると思って間違いありませんし、力学を理解せずに他の単元に進んでも学習スピードが落ちるだけです。
「力学」の最初から仕事とエネルギーの範囲までは真っ先にやり直しましょう。かといって「力学」「電磁気学」の2つを順に完璧にしていこう、と勉強し始めると大変なことになります。
「力学」も「電磁気学」も量が多く発展問題の難易度も非常に高い分野だからです。
そこで、まずはしっかり全範囲の基本レベルを、なるべく9月までには終わらせておくべきです。その上で標準レベルの問題集を完璧にしましょう。
勉強をしていく上で気を付けておきたいことは、「図を描くこと」「グラフや図から状況を読み取れるようになること」、そして「すぐに答えをだそうとせずに問題の条件を図や数式にするとどうなるか考えること」です。
公式さえ書いてしまえばすぐに答えがでてくる問題も中にはありますが、多くは「問題の条件を図や式で表した結果、求めたいものが出てくる」という流れで求まります。
公式を使って終わりではなく、この条件は図ではどうなるか、式はどう立つのか、しっかり考えていく必要があるのです。
ここで大切なことは通常の医学部で完全に初見というタイプの問題はあまり出ない、ということです。
事前にしっかり標準レベルの問題集を終わらせておけば、図の書き方や式の立て方は自ずとわかるようになっていますし、医学部特有の特殊な問題は過去問を解いた上で基礎学力がついているなら立式できるはずです。
標準レベルの問題をしっかり着実に解けるようになれば、ある時を境に点数は一気に伸びます。
1つ目の山を越えてある程度問題が解けるようになれば物理はどんどん面白くなっていくし、一度わかってしまえば同じ単元では似たような問題が多い、ということにも気づけます。
女子はどうしても物理が苦手になりがちですが、物理を通じて学べることも多いので、ぜひ楽しみながら勉強をしてください。
学習計画を立てる前にやっておくべきこと
学習計画を立てるときに重要なことは、自分の目指す大学がどのような問題を出題し、どの程度解答すれば合格するのか、という現実を知ることです。それには4月の段階で直近の過去問を解いてみるのが最適です。なかには過去問を怖がってなかなか解こうとしない人がいますが、それだといつまで経ってもゴールは見えてきません。現実と向き合い、自分が本当に行きたい大学の要求レベルを知ることが合格の第一歩です。そのうえで、自分の現状とボーダーラインとの差を明確に認識し、限られた期限までにその差を埋めるための方法を考えます。
次に、自分の弱点を知ることです。まず、それぞれの科目の学習ベースとなる教材を選びます。最初は基本だけ理解できればいいので、なるべく薄いものにしてください。そして全範囲を一通り解きながら、どの分野が弱いのかをチェックします。薄いテキストなら2週間で終わるはずです。どこが分かっていて、どこが分からないのか、◯・△・×などマークをつけながら、選別作業を一気に進めてください。最終的に問題集の目次を見ながら、どの分野が苦手なのかを瞬時に判断できるように、全範囲を体系的に見渡せるようにしましょう。
高校生の場合、学校でまだ習っていない分野もあると思いますので、余裕がなければそこだけ除外してもかまいません。ただ、難関レベルを目指す人は学校の授業進度にとらわれず、自分でどんどん進めるべきです。意識レベルの高い受験者同士の競争となりますので、高3の夏が終わるまでに全範囲を終えることが望ましいです。人よりも上に行きたければ、人と同じことをしていてはいけません。人がしない努力を積み上げていくことが絶対に必要です。その意識をもてないようであれば、難関レベルには向かないので、避けたほうが良いでしょう。単なるブランドイメージだけではなく、自分の性格や学力、体力を冷静に分析しながら自分に合った志望校を選ばないと、後々ムダに苦しむことになります。
具体的な学習計画の作り方
メディカルフォレストでは、生徒自身の学力と志望校についてのデータをもとにマネジメントミーティングを開きます。その生徒の目標設定について、直近の合格者や専門の講師たちと話し合うのですが、ここで学習目標を明確に設定するのが第一の目的です。
その際、その差をなるべく具体的な数値で表すようにしてください。たとえば、自分で解いた過去問の得点率を出して、ボーダーラインとの差が20%だとすれば、その差をどの科目でどれくらい埋められるかを個別具体的に考えましょう。また、公開模試の判定を夏までにAレベルまで引き上げ、冬までにSレベルにもっていく、などというように、達成感が得られる形で目標を設定してください。
計画表は、科目ごとに、
①学期単位
②月単位
③週単位
の3種類をつくります。長期・中期・短期と区切ることで、期限までにやるべきことをはっきり意識できます。学期単位の計画では、大まかに夏休みが終わるまでに基礎固めをする、2学期からは総合問題演習と過去問演習を始める、といったように、ゴールまでの大きな流れをイメージできるように工夫しましょう。月単位の計画では、科目ごとに使用する教材を決めたら、2か月で1周回す、というように具体的な回数を設定してください。教材の内容にもよりますが、1冊の問題集を年間通して5周以上は回したいところです。週単位の計画では、1日に何題やればいいかを決めます。1冊の問題集の総ページ数を30日で割れば、1日の問題数が分かります。短期間で細かく目標を達成することで、集中力も維持できますし、達成感によって向上心も上昇します。
計画表を自分の部屋に貼り出して可視化すると「決めたことをきちんとやろう!」という意識が強まりますし、周りに公表することで「しっかり考えて勉強しているな」という理解も得られるのでおすすめですね。また、周囲を巻き込むことで自分の言動に責任が生じてきますから、より気が引き締まりますよ。
臨機応変に動ける2割を残しておこう
計画を立てる時に、自分の可処分時間を完璧に把握できる人はほとんどいませんから、最初のうちは計画どおりにいかないのが当然です。一般的な合格者の モデルケースをベースにしたうえで、自分の適性に合うように、少しずつ学習計画を軌道修正しながら勉強を進めていきましょう。はっきり言ってしまえば、受験勉強における計画どおりの勉強は全体の8割くらいで、残りの2割は臨機応変に、走りながら考えていく、というくらいでいいのです。
たとえば、1週間のうち、月曜日から金曜日までは予定を入れ、土曜日と日曜日は空白にしておき、そこでやり残した分を仕上げる感じです。絶対に翌週に持ち越さないことが重要です。それをやると、復習する量が溜まってきて、いずれパンクしてしまいます。勉強への熱が一気に下がってしまいます。
体調が悪くてその日の範囲を終わらせられない時もあるはずですし、調子が良くて、もっとやれる!という時には、計画より多くの問題を解いてもいいのです。ただし、勉強を全くやらない日を作らないようにしましょう。1回休むと、ズルズル休んでしまうのが人間という生き物なのです。勉強を習慣化させることができれば、こんどはやらないと不安になる、という心理になります。スポーツをしている人ならわかるでしょう。一旦、運動する習慣がつき、食生活が改善されれば、意識や体質も変わり、以前のような食事ができなくなります。それと原理は同じです。
医学部受験を考えている方へのアドバイス
医学部受験では、何年もかけて勉強している受験生がいます。
もちろん自分のペースで2年3年とかけてやるのも一つのあり方です。
ただ、合格するために必要な勉強量は同じなわけで、それを3年に引き伸ばしてゆっくりやるか、一気に1年で集中してやるか、どちらがいいか学費の面からいっても体力や精神の面からいっても後者を目指すほうがいいと思います。
そのためには、趣味や遊びの時間など、多くのものを捨てなければなりません。つまり、覚悟を決めないといけないということです。
医師を目指すなら、いち早く医療現場に立って、自分のやりたいことを思う存分やったほうが実りある人生を送れるはずです。
そう思うなら、あとは行動するのみです。受験勉強はやった分だけ、結果はついてきます。努力は裏切りませんから、安心して精一杯の努力を積み重ねてみてください。
【特集】解説!医学部受験の基礎知識
-
 インタビュー母娘対談「家族の絆が支えた医学部受験」
インタビュー母娘対談「家族の絆が支えた医学部受験」 -
 学習計画【基礎固めが大事】医大生チューターが年間を通した学習計画の立て方や勉強法をご紹介
学習計画【基礎固めが大事】医大生チューターが年間を通した学習計画の立て方や勉強法をご紹介 -
 インタビュー一度軌道にのると、崩れない女子は強い!
インタビュー一度軌道にのると、崩れない女子は強い! -
 インタビュー自分の弱点を把握したら、あとは「反復」あるのみ
インタビュー自分の弱点を把握したら、あとは「反復」あるのみ -
 インタビュー学習計画を立てるポイント 力と自信をつけ受験合格へ
インタビュー学習計画を立てるポイント 力と自信をつけ受験合格へ -
 大学情報国立と私立医学部の難易度は違う?自分の学力に合わせた志望校の選び方
大学情報国立と私立医学部の難易度は違う?自分の学力に合わせた志望校の選び方 -
 大学情報私立医学部の偏差値は昔と今でどう変わった?
大学情報私立医学部の偏差値は昔と今でどう変わった? -
 インタビュー理数系科目克服のカギは「解き直し」にある
インタビュー理数系科目克服のカギは「解き直し」にある